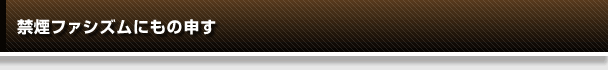禁煙ファシズムにもの申す
| 歴史に学ぶ禁煙ファシズム その1 |
小谷野 敦
先日亡くなった社会学者の小室直樹は、奇人として知られ、また天才だとも言われたが、私は若い頃、『日米の悲劇』というカッパ・ブックスを読んで、明らかに口述筆記をそのまま本にしたような、ひどいものだったので、以後ずっと関心を持たずにいた。 どうやらこれは、小室の著書の中でもひどいほうのものだったらしい。さてそれからしばらくたって、称揚する人がいるからには、ほかに主著があるはずだと考えて、人に聞いて、『危機の構造』を中公文庫で読んだ。さすがにこちらはまともな本だったが、時論的なものであるため、十年もたつと古びてしまうようなところがあって、古典的名著とは言い難い。 ただ、小室の論じ方で印象に残ったのは、現代の現象を説明するのに、歴史を用いることである。 たとえば古代のカルタゴでは、という風にやるわけである。こういうやり方はうさんくさくなりがちなものだが、小室の用い方は、あくまで例としての規矩を超えず、的確だったと記憶している。 さて、それで、歴史好きな私は、禁煙ファシズムというのは、歴史の上では何に当たるだろうか、ということをよく考える。誰でも思いつくのは米国の禁酒法だが、これが結果としてマフィアの跳梁をもたらし、十二年で潰えたことはよく知られている。 清教徒が作った国、米国ならではのことである。 もっとも、これは酒の売買を禁じただけで、呑むことは禁じてはいなかったし、今でも西洋諸国は、酒に対しては日本より厳しい。 また、十九世紀から二十世紀にかけて、喫煙者が置かれた状況というのは、明治維新の際の武士を思わせるものがある。 七〇年代の映画やテレビ番組を見ると、病室へ見舞いに来た人でも平気で喫煙していたりするが、九〇年代になると、さすがにそれはなくなったものの、それでもまだ登場人物はしかるべく喫煙していた。 先ごろ終了したらしい、NHKの朝の連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』という、水木しげるの妻を主人公にしたドラマは、ずいぶん人気があったようだが、登場人物が誰も喫煙しない、と聞いて、私はいっぺんも観なかった。 こういう環境の激変ぶりは、なるほど明治維新の五年前には、武士身分が事実上なくなるなどと想像もしなかったことに似ていて、私などはさしづめ、四十代半ばで明治維新に遭遇して、それで薩長土肥の武士たちのように得をしたわけではない、加賀藩あたりの中級武士か、幕府方の武士ででもあろうかと思う。 とはいえ、私は禁煙ファシズムが永久に続くとは思っていない。それは負け惜しみではなくて、売春や賭博がどうしてもなくせなかったという歴史を見れば分かる。 売春は、もしかするとチンパンジーですらするかもしれないという、「人類最古の職業」であり、喫煙は、せいぜいアメリカ大陸発見以後のものだが、それでもこれは、なくせないだろうと思う。 売春防止法が成立した時、人々はこれで売春がこの世から消えてなくなると思ったかもしれないが、そうは行かなかった。 今後、煙草の値段が上がるようなことになれば、恐らくヤミ煙草が登場するだろう。 日本で久しぶりに「ヤミ」というものが出現するわけで、これも興味深い。 しかしまったく不思議なのが、こうしたファシズムに反対する暴動やデモなどが起きないことで、これは、社民党や共産党が、ひときわ熱心な禁煙ファシスト団体であるところから、それらを組織する母体がない、ということで説明できる。 明治以来廃娼運動を指導してきたのも、禁煙ファシズムを根底で支えるのと同じ、中産階級の女性たちとその団体であり、市民運動の側から始まったということが、今や満洲事変以後の陸軍のように、政府を動かしてしまっているのだ。 この動きは、自由民権運動の中から右翼が生まれ、国権論が育っていった歴史を想起させる。 日露戦争の停戦のポーツマス条約は、既に日本がこれ以上戦う余力を持っていなかったため、国民にはその事実を隠し(明らかにするとロシヤにも知れるから)、ロシヤによる賠償金の支払いもなく、かろうじて樺太の南半分を割譲するという、国民が期待したものより遥かに条件の悪いものだった。 だから日比谷暴動が起き、ほとんどの新聞がこの屈辱的条約を非難する中で、これを支持した徳富蘇峰の国民新聞社は焼き打ちにあった。 日露開戦の際も、帝大七博士が開戦を勧める建白書を出しているが、伊藤博文は、「学問のあるバカほど困ったものはない」と言ったと伝えられる。(続く) 小谷野敦:比較文学者 |
| 2010/11/09 |