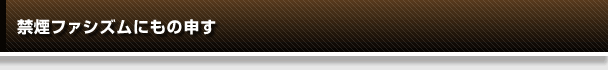禁煙ファシズムにもの申す
| ポケットに煙草(1)―分煙から排煙へ― |
僕のポケットにはいつも喫煙道具一式が入っている。紙巻ではなくパイプ煙草なのでいろいろな道具が必要なのである。左のポケットにはポーチに入れた煙草、右のポケットにはライターとコンパニオン、胸ポケットにはパイプ、と決まっている。どれが欠けても煙草を楽しめない。ライターはかならず2個でガス欠に備え、パイプ掃除用のモールも持ち歩いている。 タバコとのつき合いはもう30年になる。一日中暇さえあれば煙突のごとく煙を昇らせている僕にとって、煙が服に染み込むように、タバコは僕の生きることそのものに浸透しているといっていいだろう。仙人は霞を食べて生きているというが、僕は煙を吐いて生きている。 そんな僕には最近の日本が住みにくくなってきた。タバコの煙が嫌われだしたからである。「嫌煙権」というのだそうだが、「私は嫌いだ」というまでならよくわかる。しかし、「権利」といわれるとよくわからなくなる。僕も香水は大嫌いだが「嫌香権」を主張するつもりはない。「権利」というからには何かよほどの根拠があるのであろうが、僕にはそのあたりがどうもよくわからないのである。いい機会なので、近ごろ首を傾げていることをつれづれなるままに文字にしてみようかと思う。今回は「分煙」がいつの間にか「排煙」となるという実に面白い現象について述べてみたい。 僕は「分煙」に大賛成である。人に嫌がられてまで何としてもタバコを楽しみたいとは思わないし、楽しむからには他の人に気兼ねすることなく存分に楽しみたいと思うからである。「分煙」すれば、タバコが嫌いな人も喜び、タバコを楽しみたい人も喜べるではないか。だから大賛成である。「分煙」、これこそ成熟した社会の考え出したい大いなる知恵である。ところが最近様子がおかしくなってきた。 以前に僕が勤めていたところでこんなことがあった。タバコをやる人もやらない人も一仕事のあと集まる休憩室に、ある時「喫煙コーナー」ができた。僕らタバコ愛好者はそのコーナーで休憩するようになった。それが1年目。ところが1年目の終わりのころ「次の年から喫煙コーナーを廃止する」と予告された。僕らにとって一服することが休憩なので理由を聞くと、煙が流れてきてやめて欲しいという人がいるから、ということであった。なるほど、嫌がる人に迷惑をかけるのはよくない、僕らもその通りだと思う。しかし、このままでは屋外に追いやられてしまい休憩どころではなくなると危機感をいだいて抗議した。嬉しかったのは、タバコをやらない女性たちが署名をはじめてくれたことだ。その内容は、ちゃんとした「喫煙室」を設けるべきだ、というものであった。その結果、「喫煙室」ができた。そこは休憩室から1分もかからず移動できるところにあり、空気清浄機が2機設置され、お茶やコーヒーなどが飲めるようになっていた。これなら、タバコが嫌いな人も喜び、タバコを楽しみたい人も喜べる。「分煙」とはこうあるべきだ、と思った。なかなか見識ある処置だ、とりわけ署名をはじめてくれた女性たちには頭が下がる思いだった。ところがである、3年目にその喫煙室もなくなってしまった。理由を聞くと、喫煙室から煙が廊下に漏れ迷惑だという人がいるから、ということだった。かくして、ついに僕らは屋外に設置された灰皿の前で立ったままタバコをやらなければならないハメになった。(「抗議」を何度もしたわけであるが、きわめて紳士的に話したことはいうまでもない。その後灰皿のところに椅子が置かれたが、これでは休憩できないと抗議した結果である。) さて、僕が経験したこの経緯は、実に面白い現象ではないだろうか? みんなが喜ぶ「棲み分けの論理」から、いつの間にか一部の者を屋外へ追い出す「排除の論理」(雨が降っても雪が降っても嵐でも、タバコをやりたい者は屋外でやれ!)への移行、である。「分煙」は、僕も大賛成したように、「成熟した」社会の知恵であると思う。しかし、いつの間にか「屋外で」ということになってしまった。「分煙」を考えた人はおそらく「排除」までは意図しなかったであろう、と信じたい。しかし、結果的にタバコ愛好者は追い出され、「排除」されたのである。僕はこれを「分煙から排煙へ」と名づけている。もし「分煙」という美名の下に「排煙」を意図する社会であるとしたならば、それは「成熟した」社会であるどころか、「野蛮な」社会であるといったほうがいいであろう。そして「嫌煙権」の主張の下に「排煙」を無邪気にも愉快に思っている人がいるとしたら・・・?  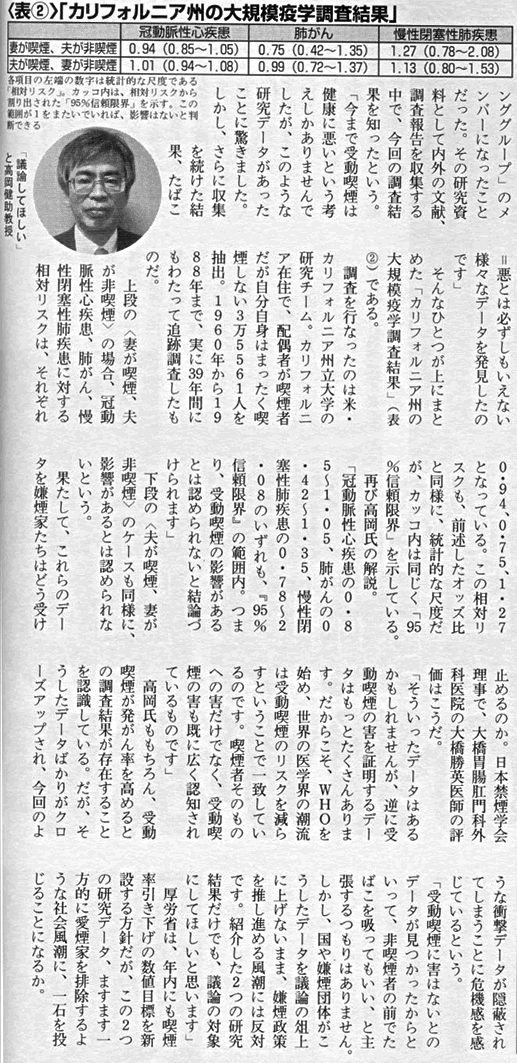 信州煙仙人(哲学者) |
| 2007/07/06 |